スマート望遠鏡「SeeStar S50」の使い方や作例について初心者向けに解説します。
スマート望遠鏡「SeeStar S50」とは

スマート望遠鏡とは、天体の電視観望に必要な機器(望遠鏡本体、電動フォーカサー、天体カメラ、制御用コンピューター、経緯台、ヒーター、光害カットフィルターなど)が1つにまとまった天体観測装置です。最大の特徴は、複雑な機材の組み合わせや設定が不要で、本体さえ購入すれば、手持ちのスマートフォンからすぐに天体撮影が始められる点にあります。
その中でも注目を集めたのが、2023年に登場した「Seestar S50」というスマート望遠鏡です。これは、天体カメラやASIAIRの開発で知られるZWO社が発売したスマート望遠鏡で、従来のスマート望遠鏡が数十万円以上と高価だった中、約6万円という驚きの価格で登場しました(現在は値上げで約85,000円)。
① 本体を設置・起動し、スマホアプリで星を指定するだけで撮影できる
(複雑な機材の準備や知識不要)
② スマホアプリだけで天体の撮影から画像処理まで行える
(PCや有料ソフトなしで、天体写真のノイズ除去や補正ができる)
③ 定期的なアップデートにより、機能が強化される
(AIノイズ除去、スケジュール撮影、モザイク撮影、4K撮影モードなど)
④ レンズや天体カメラの交換ができない(倍率固定)
「SeeStar S50」の特徴や購入レビューについては、以下ページで詳しく解説しています。

Seestar S50の解説動画は、以下の再生リストにまとめています。
本ページでは、「SeeStar S50」の基本操作から作例まで、初心者にもわかるように詳しくまとめています。
SeeStar S50の基本設定・操作
SeeStar S50の基本操作についての記事リンク集です。
基本操作
- 初期設定 & 最初に知っておきたい基本操作
- 星雲星団モードの基本操作
- 太陽モード(旧・惑星モード)の基本操作
- 4K撮影モードの使い方
- フレーミング機能の使い方(モザイク撮影)
- プラン機能の使い方(撮影スケジュール)
- AIノイズ除去機能の使い方 ⇐ 超重要
- ビデオスタックの使い方(惑星や月の写真を高画質化)
基本設定
- 「SSID」と「パスワード」の変更方法
- STAモードの使い方(SeeStar S50を子機としてWi-Fiルーターに接続)
- ファームウェアの更新方法
- PCからSeeStarを操作する方法(Mac編)
- 画像の透かし(下にあるバー)を非表示にする方法
- 「リモートコントロール機能」 ← NEW(2025/11//17)
- SeeStarアカウントの作成とログイン方法
便利ツール集
トラブル対応
春の天体(3月〜5月)と作例
春は、南東の空に銀河・球状星団を沢山見ることができます。「春の銀河祭り」などとも呼ばれています。
| 写真 | 天体番号 | 天体名 | 説明 |
|---|---|---|---|

|
M5 | へび座の球状星団 | 星がぎゅっと集まった大きな星団です。 |

|
M48 | うみへび座の散開星団 | 明るい星が点々と広がる姿が特徴的です。 |

|
M100 | かみのけ座の渦巻銀河 | きれいな渦巻模様を持つ銀河です。 |

|
M104 | ソンブレロ銀河 | ソンブレロ帽子(つばの広い帽子)のような形がユニークで、春の天体の中でも人気の高いです。 |
※天体番号もしくは天体名をクリックすると、解説ページに飛びます
夏の天体(6月〜8月)と作例
| 写真 | 天体番号 | 天体名 | 説明 |
|---|---|---|---|
 |
M8 | 干潟星雲 | 星の誕生が盛んな場所で、淡いピンク色のガス雲が広がる美しい星雲です。 |
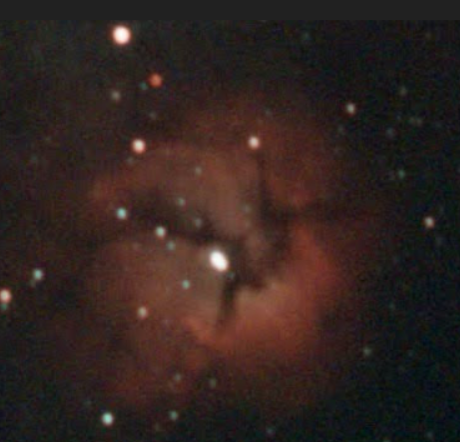 |
M20 | 三裂星雲 | 暗黒帯によって三つに分かれて見える姿が特徴で、カラフルな星雲として人気です。 |
 |
M16 & IC 4703 | わし星雲 | 「創造の柱」と呼ばれるガスの柱が有名で、星の誕生現場を間近に見られる星雲です。 |
 |
M17 | オメガ星雲・白鳥星雲 | 白鳥が羽を広げたようにも見える姿で、濃いガスと若い星々が輝いています。 |
 |
M10 | へびつかい座の球状星団 | 丸い光のかたまりのように見える星団で、望遠鏡を向けると無数の星が浮かび上がります。 |
 |
M12 | へびつかい座の球状星団 | M10と近くに位置する星団で、やや広がりのある柔らかな印象を与えます。 |
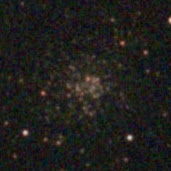 |
M107 | へびつかい座の球状星団 | やや暗めの球状星団ですが、星々が不規則に散らばる姿が独特です。 |
 |
M11 | たて座の散開星団 | 「野鴨星団」とも呼ばれ、群れをなして飛ぶ鳥のように星が集まっています。 |
 |
M2 | みずがめ座の球状星団 | とても大きく明るい球状星団で、夜空に小さな光の宝石箱のように輝きます。 |
※天体番号もしくは天体名をクリックすると、解説ページに飛びます
秋の天体(9月〜11月)と作例
秋は銀河・惑星状星雲が美しい時期です。
| 写真 | 天体番号・天体名 | 説明 |
|---|---|---|
 |
NGC 7293 らせん星雲 |
地球から比較的近い惑星状星雲で、大きな瞳のように見える姿から「神の目」とも呼ばれます。 |
 |
NGC 281 パックマン星雲 |
形がゲームキャラクターのパックマンに似ていることから名付けられた、星形成領域です。 |
 |
NGC 2237・2246 バラ星雲 |
花びらのように広がる赤いガス雲が印象的で、まるで宇宙に咲いたバラの花のようです。 |
 |
NGC 2177 かもめ星雲 |
翼を広げたカモメのような形をしていて、淡い光が夜空に羽ばたく姿を思わせます。 |
 |
M74 ファントム銀河 |
渦巻きの回転軸が地球に向いているため、渦状腕の構造が正面からはっきり見えます。 |
 |
M77 くじら座の渦巻銀河 |
中心がとても明るい活動銀河で、渦巻き模様がはっきりと見える迫力ある姿です。 |
 |
NGC 3521 バブル銀河 |
泡のように見える構造を持つ銀河で、不規則ながらも独特の美しさを放っています。 |
※天体番号もしくは天体名をクリックすると、解説ページに飛びます
冬の天体(12月〜2月)と作例
冬はM42(オリオン大星雲)、IC434・NGC2024(馬頭星雲・燃える木星雲)、M45(すばる・プレアデス星団)、M31(アンドロメダ銀河)といった定番かつ人気な天体がよく見え、空気も澄んでいるため、天体撮影に最適な季節です。
| 写真 | 天体番号・天体名 | 説明 |
|---|---|---|
 |
M42 オリオン大星雲 |
冬の夜空でひときわ目立つ星雲。肉眼でもぼんやり見え、望遠鏡では星の誕生の現場を楽しめます。 |
 |
IC434・NGC2024 馬頭星雲・燃える木星雲 |
馬の頭の形をした暗黒星雲と、炎のように輝くガス雲が並ぶ、オリオン座の名所です。 |
 |
M45 すばる・プレアデス星団 |
日本でも古くから親しまれてきた星団。青白い星々が寄り添い、肉眼でも美しく見えます。 |
 |
M31 アンドロメダ銀河 |
肉眼で見える最も遠い天体のひとつ。ぼんやりとした光のしみのように広がります。 |
 |
M33 さんかく座の銀河 |
淡い渦巻銀河で、暗い空の下なら双眼鏡でも姿をとらえることができます。 |
※天体番号もしくは天体名をクリックすると、解説ページに飛びます
彗星の作例
| 写真 | 天体番号・天体名 | 説明 |
|---|---|---|
 |
ポンス・ブルックス彗星 | 19世紀に発見された周期彗星で、扇のように広がる尾が特徴的です。 |
 |
紫金山・アトラス彗星 | 2023年1月に中国の紫金山天文台と南アフリカのATLAS望遠鏡によって発見された彗星です。 |
 |
レモン彗星 | 2025年1月にアメリカアリゾナ州にあるレモン山天文台で発見された長周期彗星です。 |
 |
スワン彗星 | 2025年秋に地球へ最接近した非周期彗星です。 |
※天体名をクリックすると、解説ページに飛びます
惑星・月の作例
| 写真 | 天体名 | 説明 |
|---|---|---|
 |
月 | 夜空で最も身近な天体。クレーターや海と呼ばれる模様が、望遠鏡でくっきりと見えます。 |
 |
土星 | 太陽系を代表する巨大惑星。土星の環を観察できます。 |
 |
木星 | 木星の大気に刻まれた縞模様を観察できます。 |
 |
太陽 | 専用フィルターを使って太陽表面に現れる黒点を観察できます。 |
※天体名をクリックすると、解説ページに飛びます
